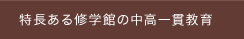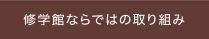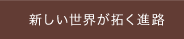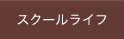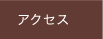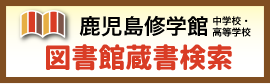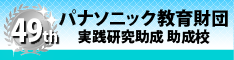- HOME >
- NEWS
本年度中学2年生は,体験学習の一環として「地域を知ろう」と題して本校周辺の地理や歴史の学習を実施しました。この学習を通して学校周辺の史跡等に目を向けるとともに,歴史や環境などについての意識を高め,愛校心や郷土を愛する心の育成につながる活動になりました。
伊邇色神社


座禅石

鹿児島刑務所跡(現西原商会アリーナ入り口付近)

午前中に地域をグループごとに分かれて探訪し,午後は原良歴史探訪会会長の吉峯栄助氏に「修学館中学校・高等学校周辺の歴史について」というテーマで話を伺うことができました。


5月8日と15日の2回、中学1年の「道徳」の時間に「いじめについて考える」授業をしました。様々な小学校から入学する本校では、いじめについてはできるだけ早く考える機会をつくりたいと考えています。学校教育目標「みんなが学ぶことの楽しさを知り、学び続ける力を身につける」の中の「みんなが」を達成するためにもとても重要です。
第1回は植松勉さん(北海道赤平市にある株式会社植松電機 代表取締役)の「思うは招く」(https://tedxsapporo.com/talk/hope-invites/)のTED動画、第2回は藤原和博さん(「教育改革実践家」東京都初の中学校の民間人校長)の「君の学校にいじめはありますか?」(スタディサプリの〔よのなか〕科コンテンツ)の動画も参考にして考えました。
授業のゴールは、IBのATL(学び方のスキル)のひとつとして示されている「いじめを防止し、撲滅する方法を実践する」には具体的にどうすればよいかを考えることです。(国際バカロレア機構がいじめ予防をスキルとして示しているということは、日本のみならず海外でもいじめはあって、どの国でも問題になっているということだということも伝えました。)
生徒のふりかえりには、「最初は、呼びかけをするくらいしか思いつかなかったけど、2回の授業が終わって、助けるのが1人では無理そうだったらまわりに助けを求める、などの考えも持てるようになったから、もし実際に見かけたら今回考えたことを実行にうつせるようにしたい」など、真剣に考えた跡が読み取れました。


【生徒記入のふりかえりより】
★小学校の道徳では、ある決まった状況でどうするか、みたいなのしかやらなかったから、いじめについてここまで考えたのは初めてだった。今までいじめの分類など考えたことなどなかったが、そのいじめの段階によって適した対策をすることが大事だと思った。いじめをなくすのは生徒だと一番感じた。
★植松さんが夢を語っている時、自分と重ねて考えていた。「絶対無理」「無理に決まってる」と決めつけない「成長マインドセット」で、こうしたら出来るかもと思考を変えてみることが大切だと感じた。
★いじめについては今までも考えたことがあったけど、2回の授業で分類したり、どうしたら減らせるのかを考えたりして、いじめについて深く考え、自分の言葉で表せたと思います。
★そもそもいじめという「わく」が広すぎるなと思った。
★僕は先週と今週の2回「いじめ」について考え、いじめは人のまぬがれない永久の課題だと思う。なぜなら、思春期や反抗期のイライラによるいじめや、不安によるいじめなど、人だったら一度は通るものが原因だから。
★私は今までいじめがないことだけがいい事だと思っていました。苫野先生も言っていたように、小さい空間で交流するのではなく、たくさんの人と交流して、自分の考えを変えたり、よりいいものにしたりしていく必要があると考えます。
★学校のレビューに「いじめが少ない」(と書いてあったような気がする)理由は、この授業の効果かもしれないと思った。
★考えれば考えるほど分からなくなるので、正解のない問いだと思った。しかし、大問題なので、正解のない問いだからと言って考えを放棄するのは違うと思う。また、たくさんの種類の「いじめ」があるので、「いじめ」の三文字で片づけてはいけないと思った。
本日4月28日、熊本大学の苫野一徳先生(哲学者・教育学者)をお迎えして、教育講演会を実施いたしました。(対象:新中1・高1生徒。テーマ:「勉強するのは何のため? 学校で学ぶのは何のため?」)本校でご講演頂くのは5年目となります。
哲学や教育学の知見を新入生の今後の修学館での学びに活かすという目的で、人類の歴史や「自由の相互承認」など難しい内容も含まれる中、たくさんのメモを取る生徒や全体の場で質問する生徒、休み時間に苫野先生を取り囲んで質問する生徒たちの姿が見られました。
講演会終了後もまだまだ話が聞きたい、苫野先生と話してみたいという生徒が集まり、さらにざっくばらんな雰囲気でいっしょにお話しました。




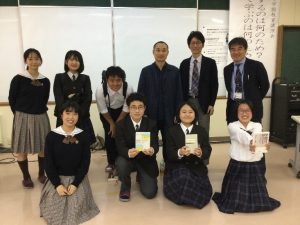
鹿児島修学館中学校・高等学校 生徒心得
鹿児島修学館高等学校 学則
鹿児島修学館中学校 学則
本校理科の南教諭が、私学教育研究所委託研究員として研究成果報告会で発表しました。
https://www.shigaku.or.jp/study/researcher_info_2022.pdf
テーマは、「IBの手法を取り入れた理科実験の授業開発」です。
組織的授業改善支援をしていただいている小林昭文先生のブログでも紹介されています。
3月26(日)に文部科学省主催「国際バカロレア推進シンポジウム」がオンライン(Zoom Webinar)で実施されます。今回のメインテーマである「なぜIB?」という点は、とても重要です。参加費無料ですので、ご都合がつけばぜひ参加をご検討ください。
【詳細】 https://ibconsortium.mext.go.jp/symposium/
【申込】 https://www.bbt757.com/svlEnquete/jsp/user/top?id=8thsymposium0326
ハチ高原を出発して大阪へ向かう道中、兵庫県養父市八鹿町にある道の駅に立ち寄りました。ここでしか買えないお土産を購入したり、肉まんを購入したりしていました。

大阪市街地に入ると景色が一変します。高層ビルが立ち並び、交通量も一気に増加。御堂筋のテールランプはとても美しく、子供達も目を輝かせておりました。鹿児島では見られない光景を見ることができました。


伊丹空港の近くでは、目の前を飛行機が通り過ぎました。

18時頃大阪市内のUSJの近くのホテルに到着し、バイキングを満喫しました。思い思いに料理を盛って、みんなお腹いっぱいになったようです。

朝7時頃、部屋の窓から。
昨夜から雪が降り、昨日とは全く違う景色でした。

新雪の上でスキー板を履くと、すこし感覚が違いましたが、子供たちはすぐに慣れて滑り始めました。

標高が高い所のスキーにチャレンジする班や、昨日滑った林間コースを走る班など、班ごとで様々な活動をしていました。
急斜面から滑り出す前の様子。先に見える白いモヤのようなものは雲でしょうか。中学2年生は、理科の授業で雲を作る実験をしました。目の前にかかる雲を見て、理科の学習内容を思い浮かべながら滑っていたのではないでしょうか。

林間コースのリフトからの風景。木々の隙間を飛んでいく野鳥の気分になれます。

急な斜面で滑る生徒たち。吹雪で遭難しそうに見えますが、全員無事です。


3時間のスキー教室を終えて、ハチ高原での活動は終了です。
インストラクターの先生方には本当に丁寧にご指導いただきました。生徒全員、3日間楽しんで活動しておりました。

ご飯を食べて、バスに乗り込み大阪へ向かいます。
大阪には18時頃到着予定です。
宿を出る時に、スリッパが箱に乱雑に入れられていました。見かねた生徒会長が友人と2人で綺麗に入れ直してくれました。流石です。

ソニー教育財団「子ども科学教育プログラム」の贈呈セレモニーが行われました。
ソニー本社にて、盛田会長から教育実践計画の助成金の目録をいただきました。
国際バカロレア(IB)教育にも関係する内容です。
IBをはじめとする教育活動の充実に有効活用します。

詳しい内容については、以下のページで公開されていますのでご参照ください。
学校法人津曲学園 鹿児島修学館中学校(鹿児島県)
テーマ:「中学生の転移スキルや定義・分類する力を育む多教科で実践しやすい教科横断的授業」